通夜・葬儀・告別式でやるべきこと。
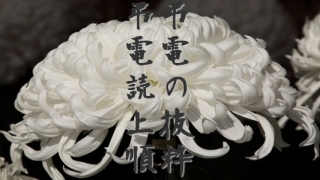
弔電の抜粋・弔電読上げ順を決める
告別式中に読上げられる弔電を抜粋し、弔電を読上げる順番を決めておく。順番は親族、各種団体としておいた。また弔辞がある場合 ...
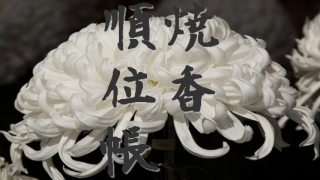
焼香順位帳の作成
告別式での親族焼香順、団体代表焼香順を決め、それぞれ焼香順位帳を作成する。おおまかな焼香の順番は喪主、遺族、親族、留焼香 ...

通夜式々次第・通夜について
通夜式々次第、通夜に関すること。通夜式自体はこれといって注意するべき点はないが、葬儀会館で通夜をおこなっているので葬儀会 ...
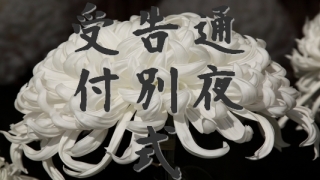
通夜・告別式の受付
通夜受付・告別式受付それぞれ受付役員の方にしていただくことについて。香典辞退していたので通夜では弔問名簿に記帳してもらい ...
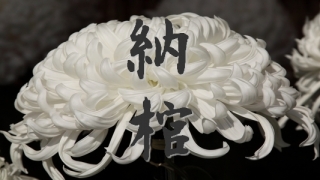
納棺 葬儀式場に向う
通夜当日午後4時葬儀社の寝台車が自宅に迎えに、葬儀社の葬儀式場に向う。葬儀式場に着いて納棺を行う。父を棺に安置、自宅より ...

通夜は友引でもおこなう
通夜は友引でも行われる。本来の友引の意味は友を曳くという意味ではないのだが、元々の友引の意味は縁起が悪い日という意味では ...

通夜・葬儀の受付役員の手配
通夜・葬儀の受付役員をしていただけないか隣近所にお願いして回る。有難いことにすぐに快く受けていただく。ありがたいことであ ...

葬儀委員長なし 香典は辞退
葬儀委員長は立てないことにした。一般の方からのご香典はご辞退。祭壇、遺影、棺、骨壷、通夜料理・精進落し料理・お寺様用和菓 ...

仮通夜
臨終の日の夜が仮通夜となる。枕飾りの一本の線香と蝋燭を絶やさないように亡くなった人と家族・近親者で過す。玄関には忌中の紙 ...


